どうも、海の藻屑(もくず)となる夢を見た元栄養士のおもちです。
今回は、もずくの注目すべき栄養効果や効果的な食べ方について紹介します。
食べ過ぎによる危険性やもずくと食べ合わせたいおすすめ食材なども、よかったら参考にしてみてくださいね。
もずくの栄養と期待出来る効果

もずくは体に良いイメージはありますが、どのような栄養や効果があるのでしょうか。
食べ過ぎによる危険性やおすすめのもずくも参考にしてもらえたら、嬉しいです。
ぬめり成分や色素成分に注目
もずくには特有のぬめりがありますが、その正体は水溶性食物繊維の一種であるフコイダンやアルギン酸です。
水溶性食物繊維は糖質の吸収をゆるやかにし、余分なコレステロールを体外へ排出する働きがあります。
またもずくや昆布、わかめなどの褐藻類の色素成分は、抗酸化力のあるフコキサンチンです。
他にも免疫力向上に役立つβ-カロテンや骨の健康維持には欠かせないカルシウムやマグネシウムなどのミネラルを多く含み、様々な生活習慣病予防に期待出来ます。
ヨウ素の過剰摂取に注意
もずくにはヨウ素が豊富に含まれています。
ヨウ素は甲状腺ホルモンの構成成分であり、全身の新陳代謝を高めるために必要不可欠の栄養成分です。
ただ、過剰摂取は甲状腺機能の低下へ繋がるので注意しましょう。
あくまでも目安ですが、市販のもずく酢だと1日1パック(70g)程度が良いでしょう。

もずく酢は砂糖や塩分も入っているから、食べ過ぎには気を付けよう!
塩抜き不使用のもずくがおすすめ
もずくには塩蔵タイプと塩抜き不使用のものがあります。
水溶性食物繊維や熱や水に弱い栄養は、洗う際に流れ出てしまう可能性があります。
塩抜き不使用のもずくは、手軽かつ栄養も摂れるのでおすすめです。
【沖縄産 太もずく】
※食べ切れない場合は冷凍保存しましょう。
【JF 沖縄漁連 沖縄乾燥もずく】
※乾燥・小分けタイプで便利です。

塩抜き不使用はありがたい♪
冷凍や乾物を利用すれば、好きな時に食べられて続けやすいね!
もずくにちょい足しで、さらに栄養アップ!食べ合わせにおすすめな食材とは?

もずくはさっぱりした味わいだからこそ、つい食べ過ぎてしまいます。
他の食材と上手に組み合わせて、栄養バランスよく効果的に摂れたら良いですね。
もずくと組み合わせたい食材は以下の通りです。よかったら参考にしてみてくださいね。
- もずく×塩昆布
- もずく×納豆
- もずく×トマト
- もずく×玉ねぎ
- もずく×きのこ
- もずく×卵
【もずく×塩昆布】
昆布にも水溶性食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。
浅漬けなどに入れる塩の代わりに塩昆布を使えば、旨味や栄養がアップします。
色々な海藻と組み合わせて摂りたい時におすすめです。
【もずく×納豆】
納豆菌ともずくの食物繊維により、腸内環境を整える効果が更にアップします。
納豆に含まれるビタミンKはカルシウムの吸収も高める作用があり、骨の健康に役立ちます。
あわせて読みたい>>納豆の栄養効果
【もずく×トマト】
トマトには美容や健康にいいビタミンCや抗酸化作用のあるリコピンが豊富に含まれています。
もずくにはこれらが含まれていないので、相加効果が期待出来ます。
リコピンは加熱により吸収率が高まるので、スープがおすすめです。
鶏のささ身など、お肉も入れればたんぱく質も摂れて食べ応えも増します。
【もずく×玉ねぎ】
玉ねぎにはアリシンという辛み成分が含まれています。
殺菌作用や抗酸化作用があり、生活習慣病予防に役立ちます。
薄くスライスした水さらし玉ねぎともずくのサラダ等がおすすめです。
【もずく×きのこ】
きのこには不溶性食物繊維が豊富に含まれています。
もずくの水溶性食物繊維と合わせて摂ることにより、腸内環境が整い便秘対策に効果が期待出来ます。
マリネにすれば、お酢の健康効果も期待出来るので一石三鳥ですね。
あわせて読みたい>>お酢の使い分けについて
【もずく×卵】
完全栄養食品と呼ばれる卵ですが、食物繊維は充分とは言えません。
かきたま汁等、もずくと合わせることにより栄養バランスがより整った食事になります。

是非色々試してみてね♪
トマトのもずくポン酢ジュレのレシピ

材料と作り方やポイントは以下の通りです。
材料(2人分)
- もずく 100g
- 新鮮なトマト 2個
- ポン酢 大さじ3
- ゼラチン 5g
- 柚子胡椒 小さじ1/2
- 80度以上の湯 50ml
- 水 200ml
- 小ねぎ お好み
- おろし生姜 お好み
作り方
- Step1ポン酢ジュレを作る
- Step2トマトの器を用意する
- Step3トマトの器にもずくとジュレを盛り付けて完成
- ジュレを冷やし固める器に、ポン酢・柚子胡椒を入れてよくかき混ぜる
- 1に80度以上の湯50mlを入れて、ゼラチンを少しずつ溶かし入れた後、水を200ml入れる⇒冷蔵庫で30分以上冷やす

- トマトを写真のようにくり抜き、器にする

- もずく、くり抜いたトマト、冷蔵庫で冷やし固めたジュレを盛り付ける

- ねぎ・おろし生姜を乗せて完成


ジュレがキラキラしてキレイだよ☆彡
暑い夏にさっぱりと味わえる一品!
もずくはちょい足し食材と一緒に栄養バランス良く食べよう!
もずくのぬめり成分には、フコイダンやアルギン酸などの水溶性食物繊維が豊富に含まれています。
しかしもずくに含まれるヨウ素の過剰摂取は、甲状腺ホルモンの機能性の低下に繋がるため適量を心掛けましょう。
他の食材と上手に食べ合わせることにより、栄養バランスが整いますよ。
もずくを楽しむ際には、塩抜き不使用のもずくを使ってみるなど、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。


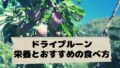

コメント